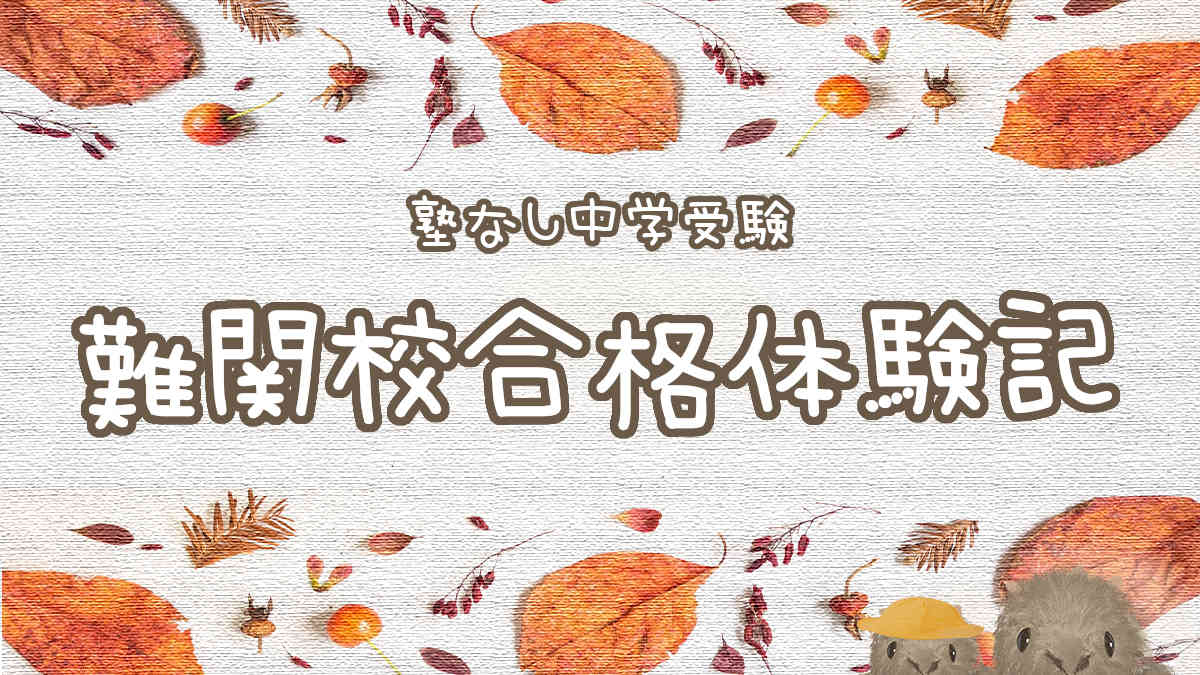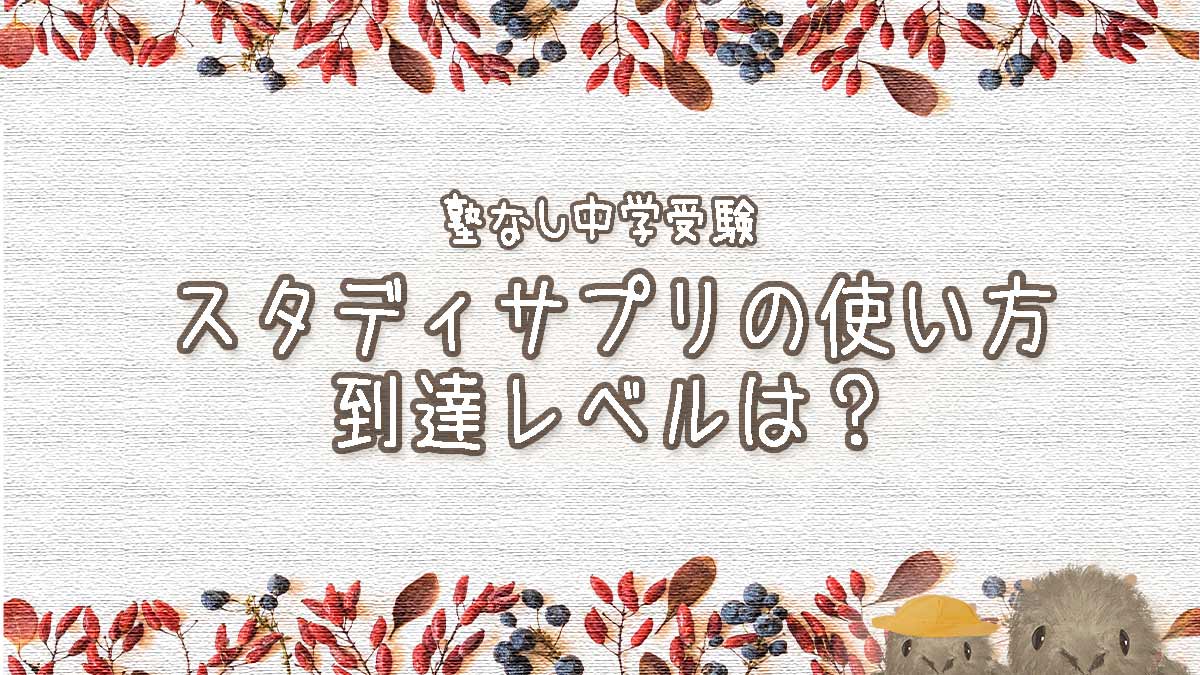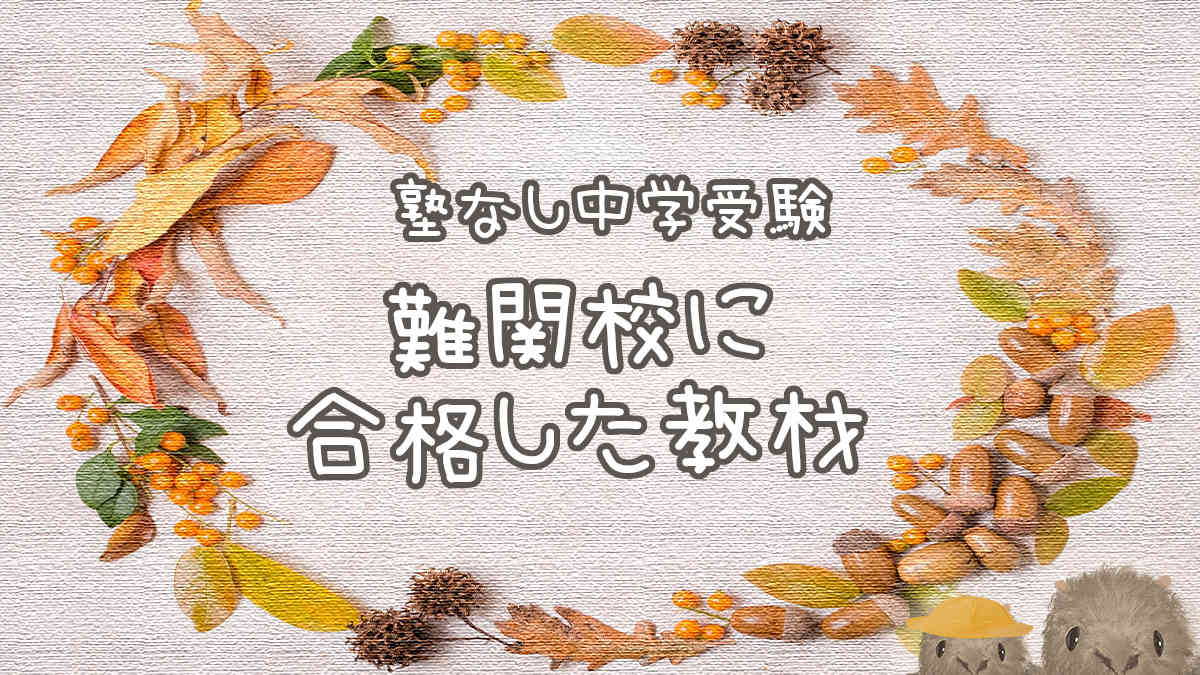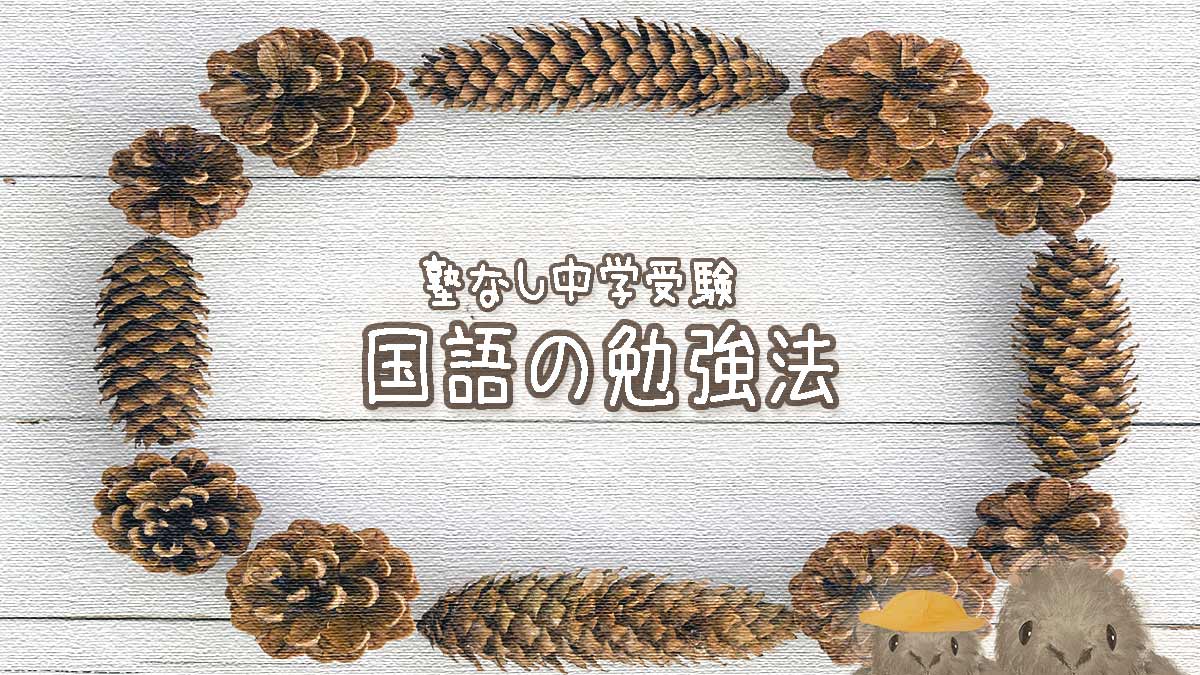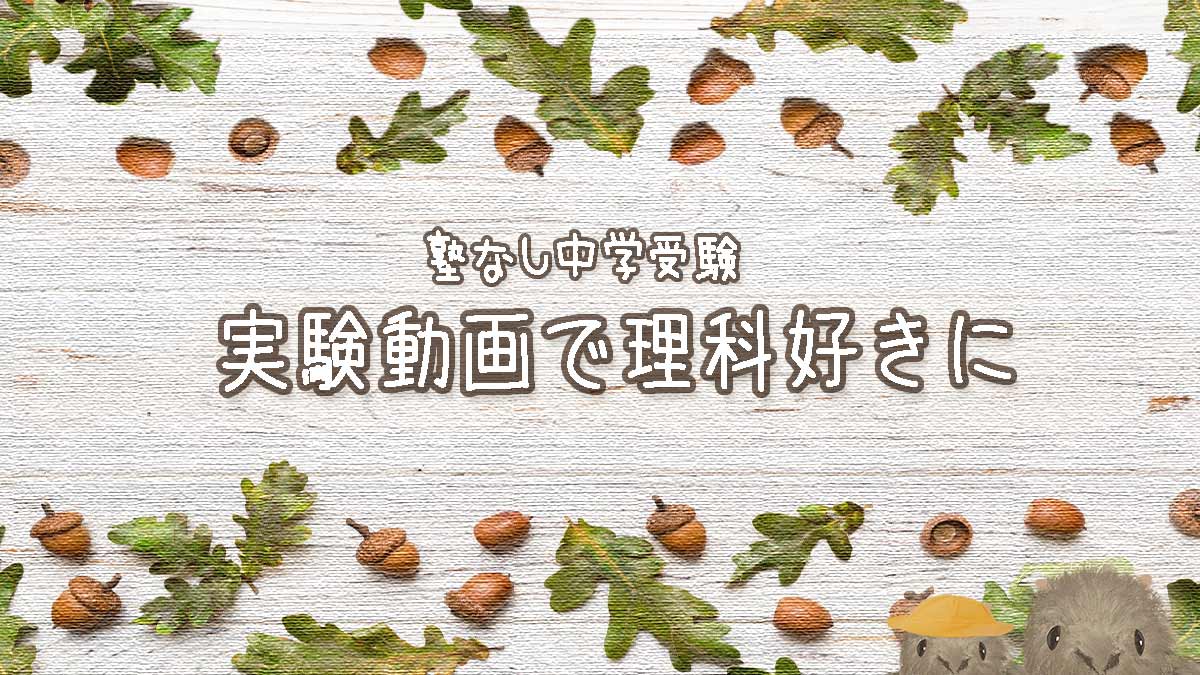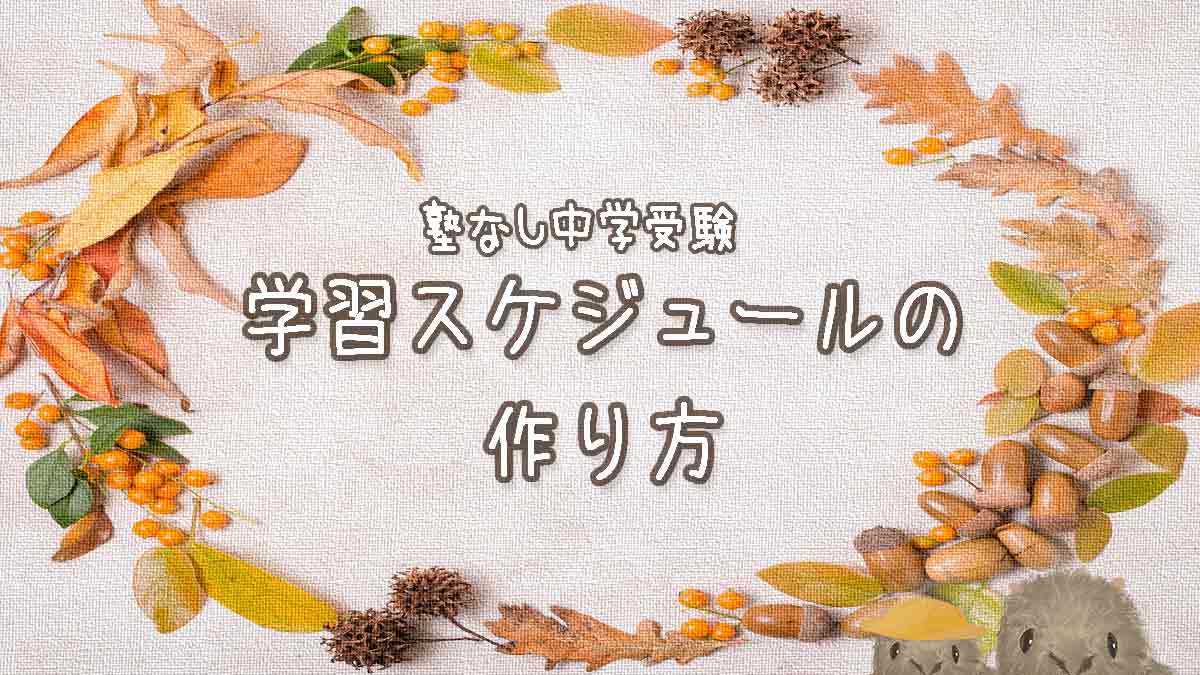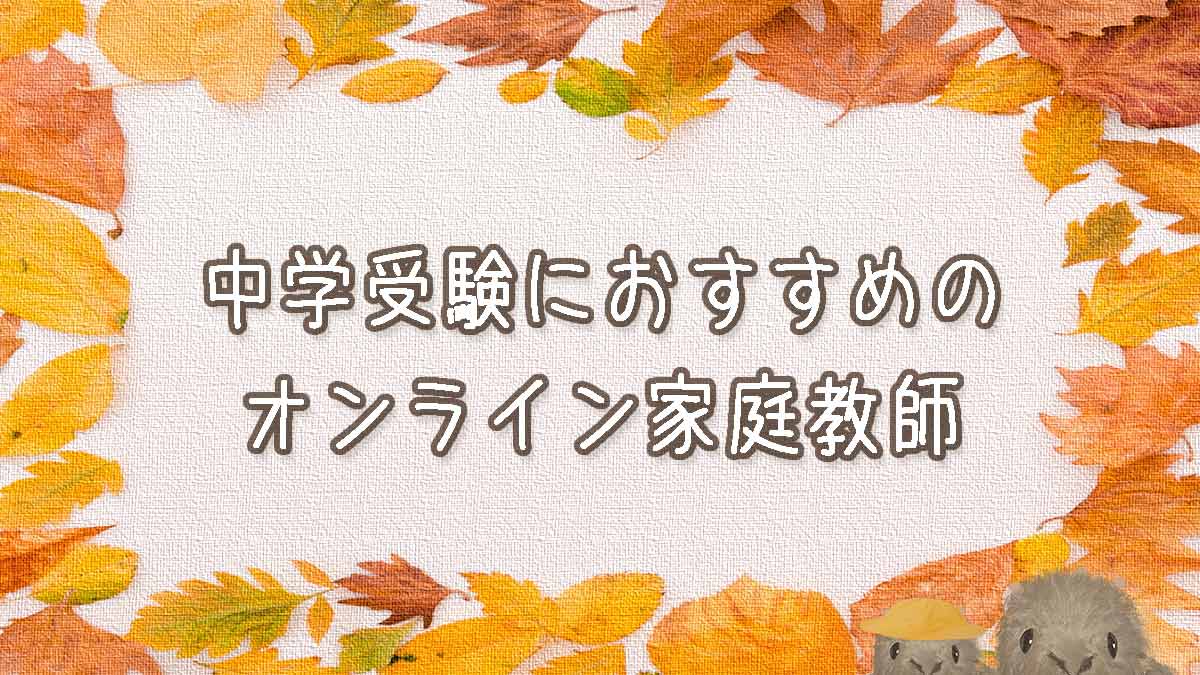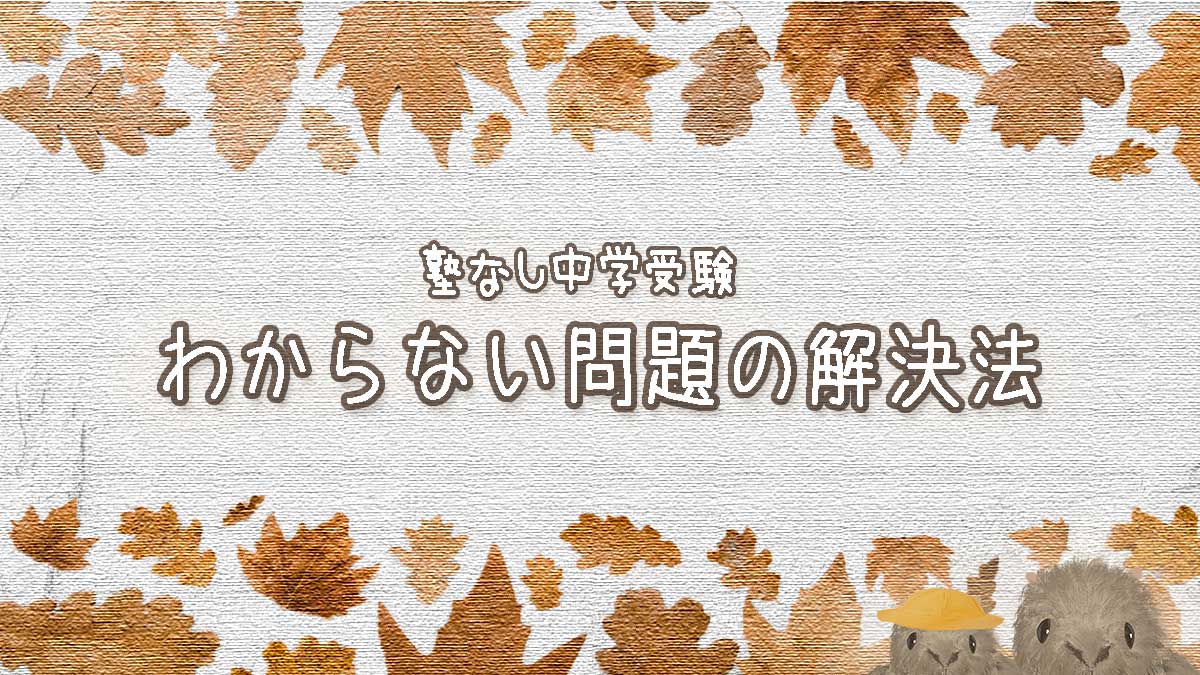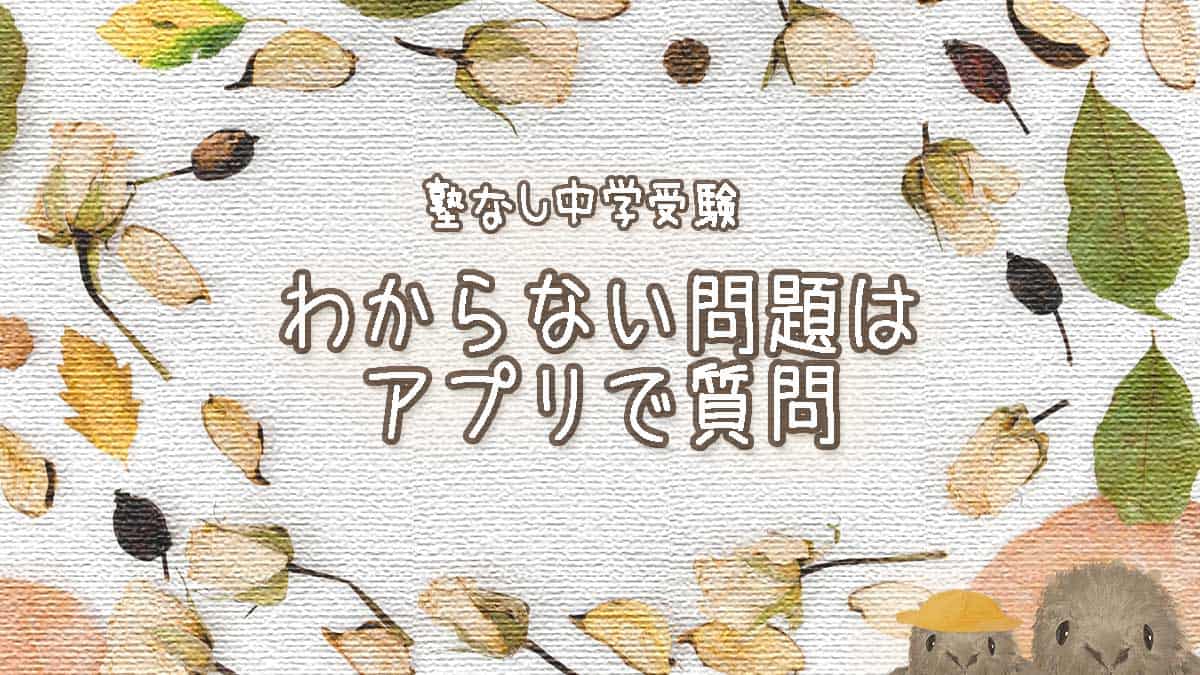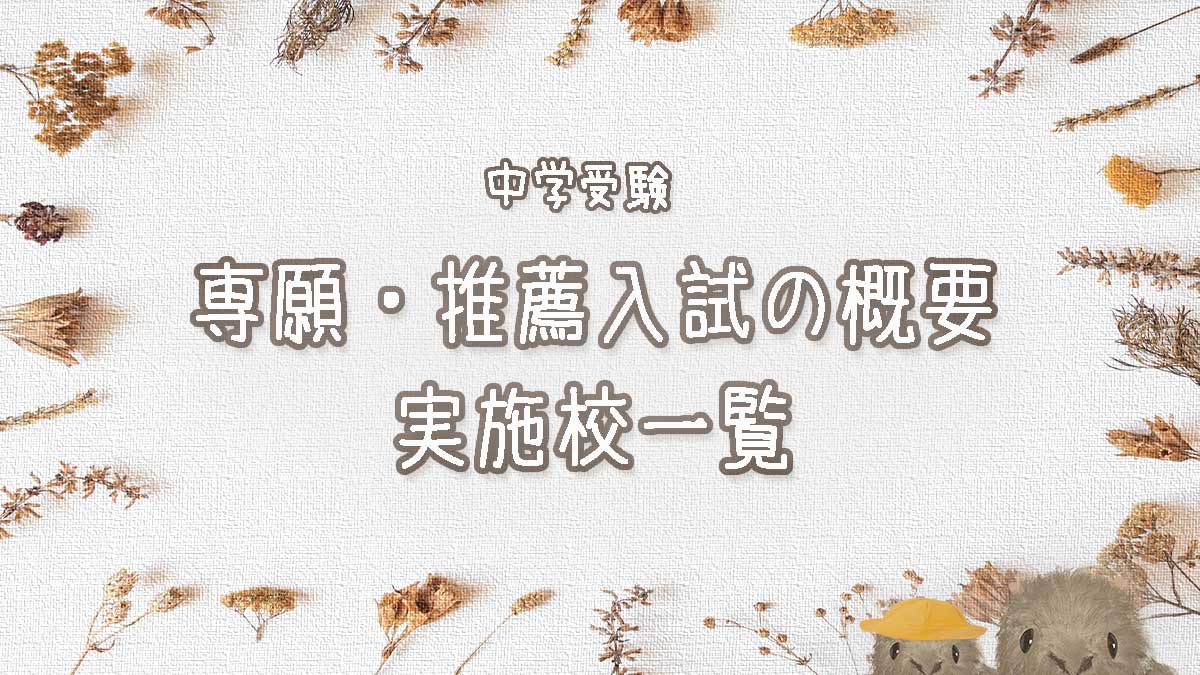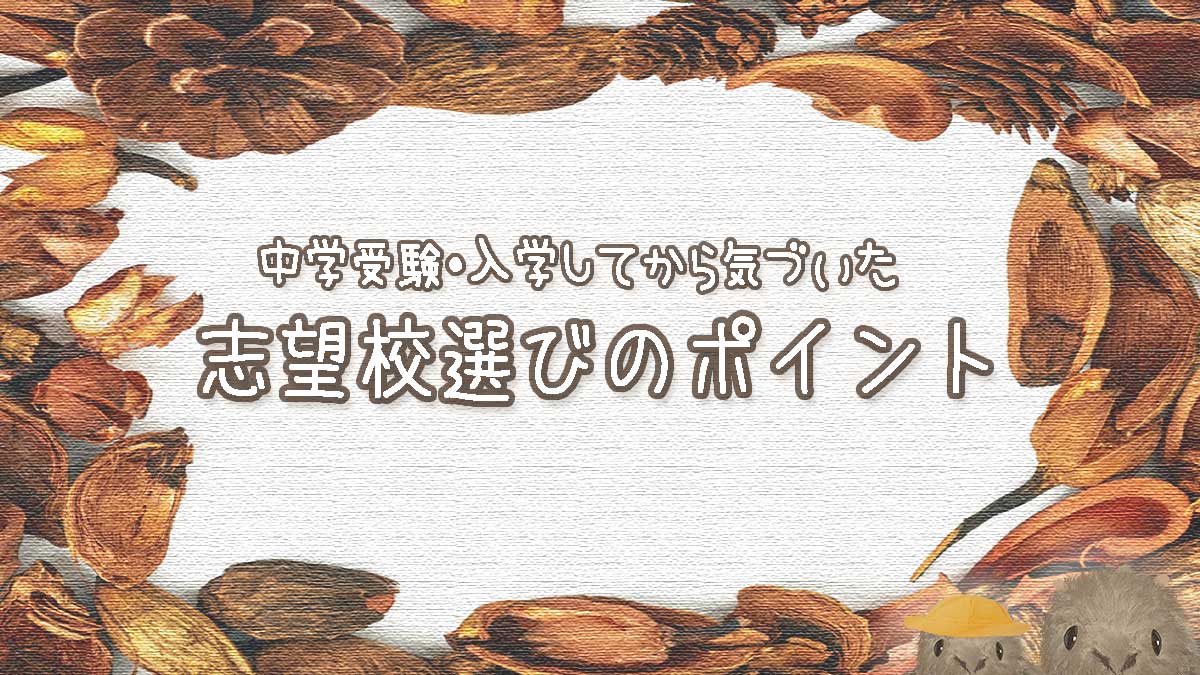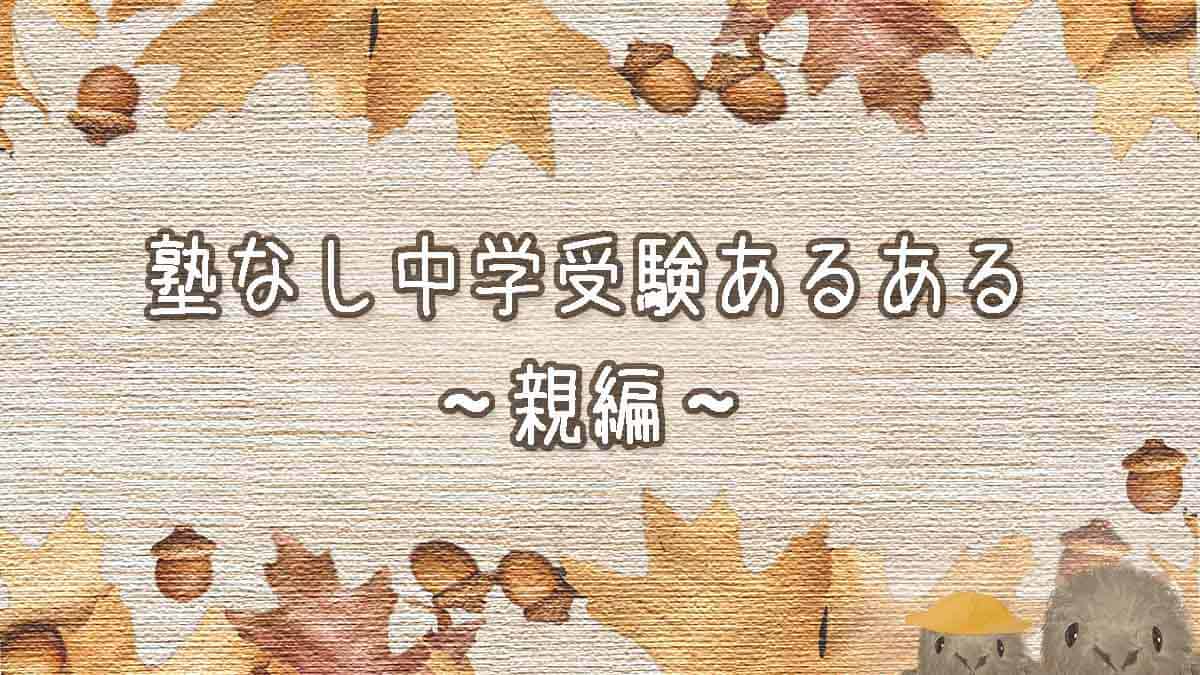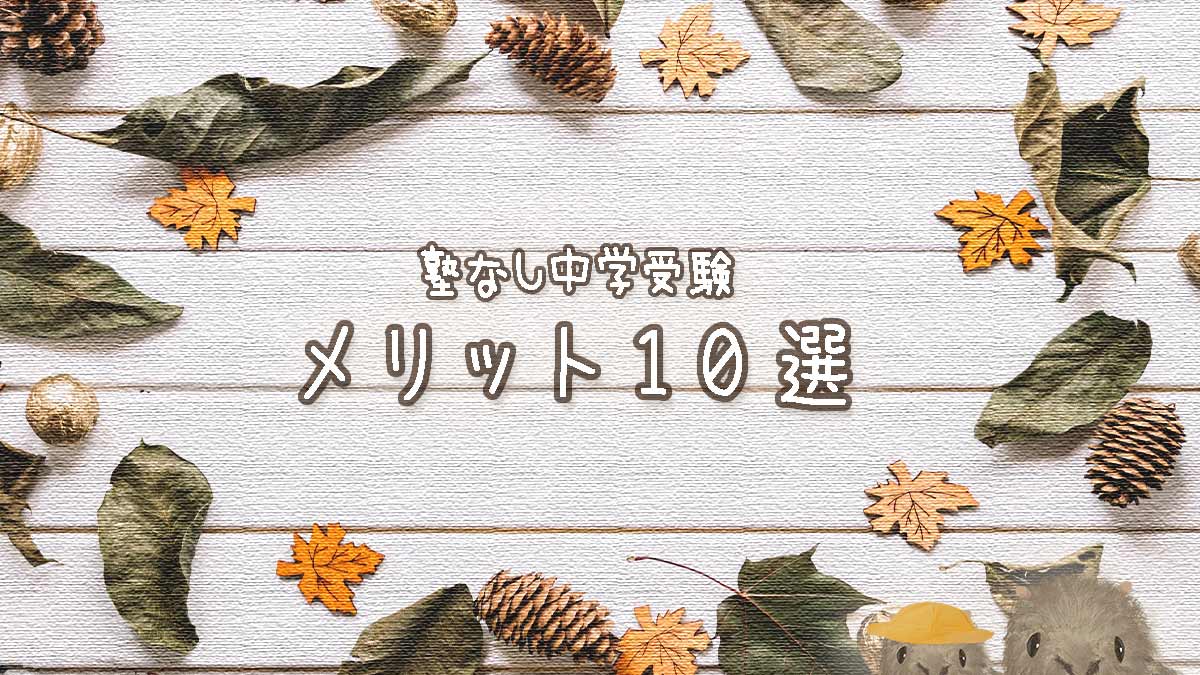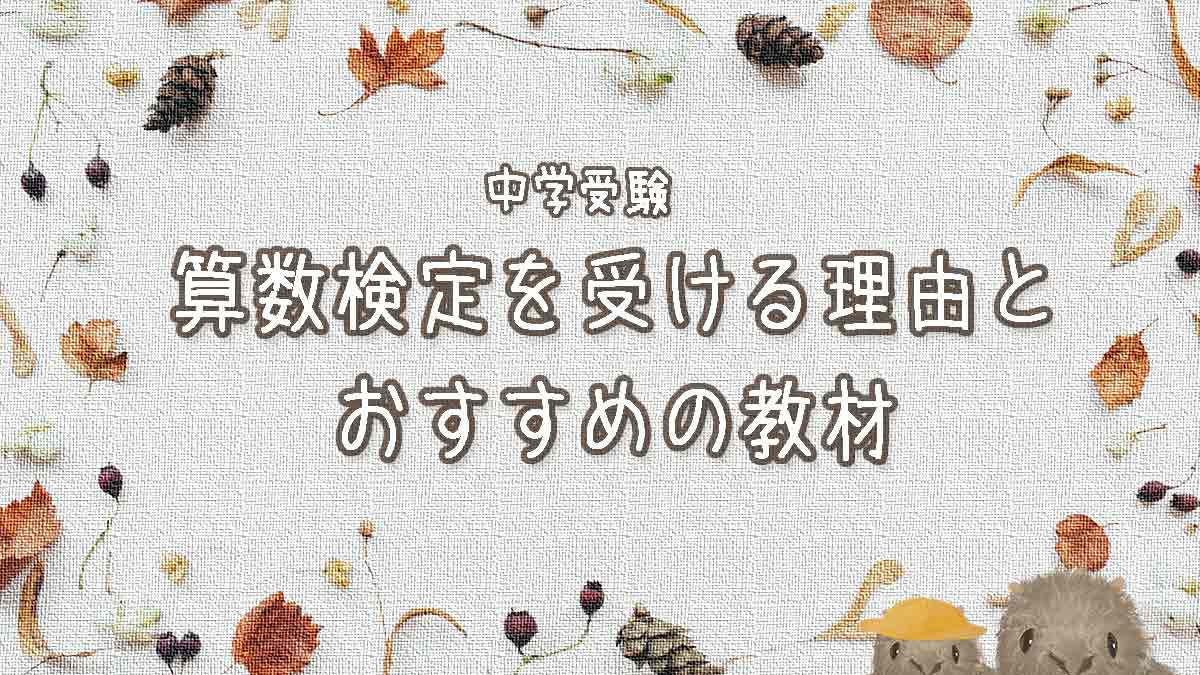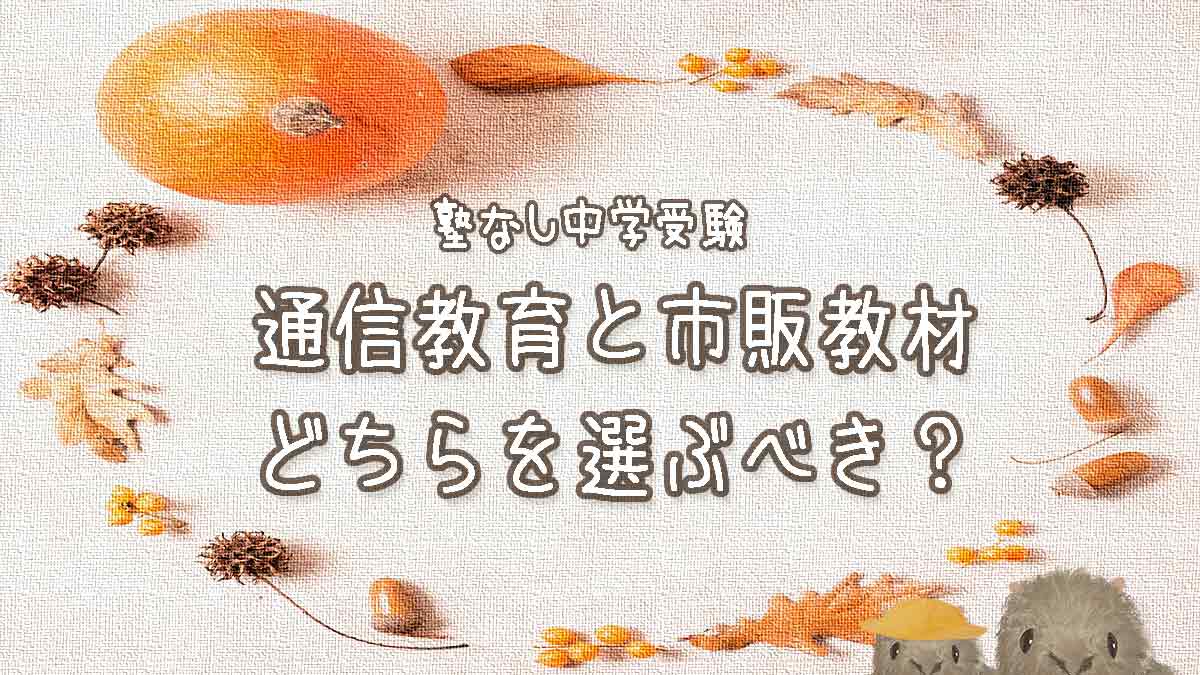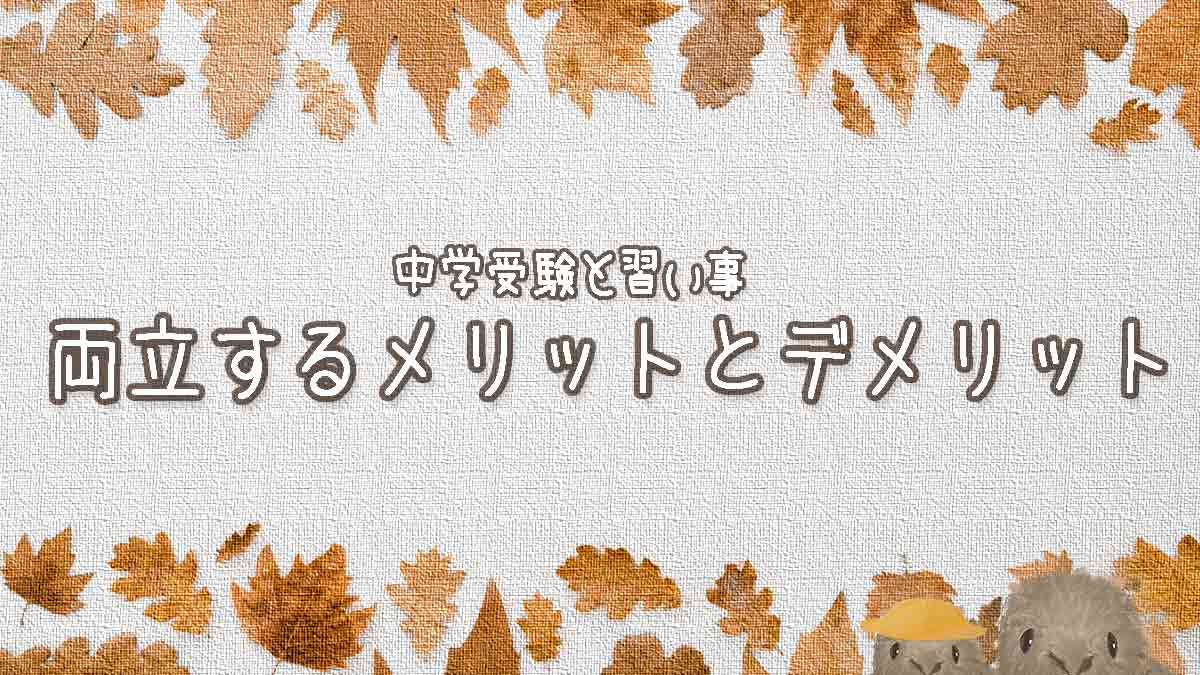はじめまして、塾なし中学受験をしたこもんがです!
こもんがは、小6の夏休みまで週5回の習い事を続けながら塾なし中学受験をして、Z会で難関校レベルとされている学校に合格することができました。

塾なし中学受験と聞くと、志望校に合格できるのか疑わしいイメージがあるかもしれないですね。

ままんがも塾なし中学受験を終えるまではそう感じていました。
でも実際に受験を終えてみると、塾なしだったことにより個別最適化された学習が実現でき、結果として最短距離で難関校に合格できる力がつけられたと感じています。
この記事は、その時の経験をもとに塾なし中学受験の方法をまとめたものになります。
塾なし中学受験に興味がある人は、実体験の一例として参考にしてみてください。
教材選び
まずは塾なし中学受験をした時に使った教材の選び方についてです。
こもんがが中学受験した時は、家庭内に勉強を教えられる人がいなかったこともあり、解説がわかりやすい教材を選ぶようにしていました。
実際に教材を使う時には以下のような点も考えるようにしていました。
塾なし中学受験の教材を選ぶときに気をつけたこと
基礎の取得や解法の幅を広げるなど、それぞれの教材で学ぶ目的を明確にする。
その時点の実力にあっている教材を使う。
力をつけるために本当に必要な、最小限の量の教材を使う。
同じレベルの問題集を複数使わない(同レベルの場合切り口が違うものを選択)
また、参考書や問題集だけでなく動画、アプリなど自分達が使いやすいと思ったものは積極的に取り入れ、特に算数はスタディサプリで基礎を固めました。
なお、実際に使った教材の詳細については長くなってしまうので以下の記事にまとめてあります。
興味がある方はぜひご一読ください。
塾なし中学受験の勉強法について
塾なしの場合、教材だけでなく学習方法も自分達で決めることになります。
学習方法については、大きく分けて以下のような選択肢から選ぶことになります。
参考書や問題集を使って独学で勉強する。
問題集と動画などのICT教材を併用し独学で勉強する。
通信教育を利用する。
基本的に問題集や動画などのICT教材を併用して勉強するが、部分的に家庭教師などの手を借りる。
一番大切なのは「自分達に合っている方法で勉強する」ことなのですが、こもんがの場合は「問題集と動画などのICT教材を併用し独学で勉強する」という方法で学習を進めました。
具体的には、算数はスタディサプリ、理科は実験動画、暗記はアプリを利用するなどして、教科や学習の特性に合わせた学習方法を取り入れるようにしていました。
学習する内容の優先順位
こもんがの場合、習い事を続けながらの中学受験だったので勉強に充てられる時間が限られていました。
そのため、本番で点数を稼ぐことを意識して学習内容に優先順位をつけていました。
具体的には以下のようになりますが、こもんがと同じように勉強に使える時間が限られており、正攻法での受験勉強が難しい人は一例として参考にしてみてください。
理科と社会 → 傾斜配点により配点が低い事が多いので、ギリギリまで勉強時間を削り記憶のメンテナンスにかかる時間を省く。また、得点源になりそうなことから学習を進める。
算数→どの学校でも配点が高いので、基礎固めから時間をかけて勉強。
なお、各教科ごとの具体的な学習方法は、科目別の記事に詳細をまとめてあります。
興味がある方は、ぜひご一読ください。
塾なし中学受験の学習計画について
学習計画は、基本的には以下のような考え方を基本にスケジュールを組みます。
ただ、正直なところ、単元ごとの難易度や志望校で求められるレベルについて理解できていない親が完璧な学習計画を立てることはかなり難しいのではないかと思います。
参考までに、こもんがも予定外の基礎の学び直しをすることになったりと、なかなか計画どおりに学習が進みませんでした。
この時の経験から、中学受験のプロではない親が塾なしの計画を立てる場合、余裕を持った計画を立てることがポイントになると感じています。
なお、学習スケジュールの立て方については以下の記事に具体的な手順をまとめてあるので、スケジュールの作成方法が思い浮かばない方は参考にしてみてください。
勉強そのものに関心が集まりがちな中学受験ですが、非現実的な学習計画を立ててしまうと受験本番までに必要な力をつけることができません。
スケジュールの作成や進捗管理は受験生活の要のひとつです。
もし、自分でやる自信がない、または不安な場合は、受験生活全般のサポートも含めて週1程度プロのアドバイスを受ける機会を設けておくのもおすすめです。
訪問、または通学型の家庭教師や個別などの利用も良いですが、オンライン家庭教師の場合移動にかかる時間も節約でき料金も抑えめなので検討してみても良いと思います。
塾なし中学受験でわからない問題があった場合どうするか
塾なし中学受験を考えている場合、「わからない問題があった場合にどうすれば良いのかな?」って疑問に思いませんか?
こもんがの場合、家庭教師や塾などは全く利用しなかったため、わからない問題は自分達だけで解決する必要がありました。
具体的には、問題の難易度の見直しや繰り返し学習、基礎の確認など地道な作業を繰り返しつつわからない問題に対応していました
そして、何をやっても理解できない問題については、打つ手なしであきらめたこともありました。
》【塾なし中学受験】わからない問題はどうするの?質問できる?解決方法6選
でも、自分たちで解決できないことは無理せず外部の手を借りたほうが効率的で、精神的に余計な負がかかりません。
特に、わからないところをアプリで質問できるラクモンや、中学受験の指導経験者によるスポット的な指導が受けられるココナラ ![]() のようなスキルマーケットは、積極的に利用することをおすすめします。
のようなスキルマーケットは、積極的に利用することをおすすめします。
》ラクモンとスナップアスクの賢い使い方〜わからない問題が質問できる!
過去問への取り組み
過去問への向き合い方は様々だと思うのですが、こもんがの場合、5年生の始めくらいまでには興味のある学校の過去問を取り寄せて出題傾向を把握しておき、普段の学習を通して志望校の出題傾向に合わせる学習をしていました。
過去問を解き始めたのは2学期の後半なのですが、いきなり本命校の過去問を解くのではなく、本命校と出題傾向が似ている学校の過去問を使い、4教科を通して解くことに慣れてから、本命校の過去問題に取り組むようにしていました。
また、実際に志望校の過去問を解くときには本番の予行演習も兼ねてて、本番となるべく同じ条件で取り組みました。
具体的には、本番と同じ時間割、スケジュール、文房具、時には入試本番で着る予定の服を着て、気になる点がないかを確認していました。
塾なし中学受験における先取り学習について
先取り学習については賛否両論あると思うのですが、塾なし中学受験をする場合には、中学受験の勉強を始める前に、最低限の内容は理解しておくことを強く推奨します。

こもんがは、先取り学習なしで中学受験の勉強をしたのですが、特に算数においては学習効率が悪くて相当痛い思いをしました。
もしかすると、中学受験の勉強を始めるのが小5だったり、小6からといった場合は先取り学習なしでもそれほど困ることはないかもしれないです。
でもこもんがのように小4から中学受験の勉強を始めた場合、特殊算の思考を整理するために必要な面積図が書けなかったり、少数と分数の計算、または分数同士の計算ができなかったりと、足りない知識を補填するためにその都度学習が中断されます。
この辺りの話についてはとても長くなってしまうので、以下の記事にまとめてあります。
特に小4以前から中学受験の勉強を始める人はぜひご一読ください。
》【塾なし中学受験】先取り学習なしで後悔したこれだけはやっておくべきこと
模試を受ける
塾なし中学受験の場合は、塾のようなクラスわけもなく一緒に勉強している仲間もいないので、自分の立ち位置がまったくわからないです。
なので、自分のレベルを把握するため、それから試験に慣れるためにも模試の受験は必須です。
大手進学塾で毎月のように行われている模試や公開テストは、塾に通っていなくても塾の公式サイトから申し込むことができるのでぜひ受けておいてください。
偏差値は高めに出ますが、とりあえず、無料で受けられる全国統一小学生テストで腕試しをしてみても良いかもしれないですね。
また、志望校別模試については進学塾が開催しているもの以外にも、中学校がプレテストみたいなのをやっている場合もあるので、志望校で開催がある場合は参加してみてください。
ちなみに、推薦入試で受験する場合はプレテストの受験が出願の条件になっている学校もあるので、早めに情報を集めておくことをおすすめします。
》中学受験の専願入試・推薦入試とは?メリット・デメリットと実施校一覧
志望校を決める
志望校を決めるにあたっては学校の進学実績や難易度に目がいきがちなんですけど、実際に入学して見るとほかにも大事なことはたくさんあると感じました。
特に、入学するまでは全く想像できなかったのですが、学校の指導方針は学校生活を送る上でとても影響が大きいです。
指導方針というとわかりづらいのですが、大きく分けると以下のふたつに分けられます。
学校主導の指導方針。
生徒の自主性に任せた指導方針。
勉強面での例を挙げると毎朝の小テストや連日の補習があり、膨大な量の宿題が出るような学校は学校主導型、宿題や課題、補習もほぼない学校は自主性に任せるタイプの学校になります。
また、中学校はがっつり学校主導でも、高校になると生徒主導といった一貫校も存在します。
いずれにしても合わない方の学校に入ってしまうと子供が苦痛に感じてしまうので、志望校選びの際は確認しておくことをおすすめします。
海外大学進学を視野に入れる中学受験の注意点
海外の大学は高校の偏差値とは関係なく成績により出願の可否が分かれます。
そのため「とにかく偏差値の高い学校」という学校選びではなく、より良い成績が取れる学校を選ぶ方が出願できる大学が増えます。
また、海外大学といえばバカロレア(IB)校という風潮もありますが、IBカリキュラムは多忙でかつ理系を目指す場合には、選択できる科目が少なく大学出願時に不利になります。
他に、イギリスやオーストラリアなど英系の大学目指す場合は日本の高校卒業資格では直接入学できず、1年間の準備コースを経ることになります。
そのため高校卒業後、英系の大学に直接入学したい場合はSATやAP対策をしている広尾学園やAレベルプログラムのある静岡聖光学院のような海外の大学入学資格取得をサポートしている学校を選択しても良いかもしれません。
ただ、同じ学校に海外進学者の希望が多いと奨学金の面では競争相手が多く不利になるのでその点はよく考える必要があります。(欧米の大学は年間の学費が400万〜500万円かかります)
なお、学校のカリキュラムであるIBと異なり、AレベルやSATは資格試験なので日本の高校に通いながら通信教育などを利用しながら取得することも可能なので、余裕のある学校に入学し自分で取得するのもおすすめです。

英文の推薦書や書類が必要になる場合もあるので、海外大学進学に理解がある学校がおすすめです
情報収集
塾なしだと情報が手に入りづらいというのは一昔前の話で、中学校の公式サイトや私学協会、大手進学塾が運営するサイトなどを利用して情報を集めることができます。
大手進学塾の情報
大手進学塾から発信されている情報は、宣伝っぽいものや学力型入試偏重気味な面は否めないのですが、通塾組がどんな種類の情報に触れているのかを知っておきたかったこともあって一通り目を通していました。
志望校からの情報
そのほかにも、学校主催の説明会や体験授業、文化祭といったイベントにも参加しました。
当然かもしれないんですけど、募集要項と公式サイト、学校に足を運んで得られる情報が一番役に立ちました。
中文際や体育大会
志望校が中学校総合文化祭や中学校体育大会などに参加している場合は、観に行くと生徒たちの普段の様子がわかります。
特に習い事をしていて入りたい部活があるような場合、先輩たちが活躍する姿を見ることは子供にとって大きな刺激になり「絶対にこの学校に合格したい」という気持ちになりやる気スイッチが入るようです。
県別と全国があるのですが、県別に開催されているものだと自宅からも観にいきやすいのでおすすめです。
塾なし中学受験における親の役割
塾なしで受験をする場合、情報集めから教材の選定、学習面でのサポートまで、親がやらなくてはいけないことはたくさんあります。
塾や家庭教師を利用していても親が子供をサポートする必要はあるんですけど、塾なし中学受験の1番の特徴は「親に対してのサポートが何もない」ところです。
そして、やり方がわからない、迷いがある、悩んでいる、行き詰まってしまったという時も、自分でなんとかする必要があります。
なので「中学受験の目的が塾なし中学受験すること」ではない限り、きついと感じた時は家庭教師や個別指導などの助けも借りて乗り越えていくことをおすすめします。
》中学受験に使えるおすすめのオンライン家庭教師一覧と失敗しない選び方【厳選版】
まとめ
こもんがが中学受験をした頃は、塾なしで中学受験をするのは無謀という考え方が一般的でした。
でも最近は、ネットを利用して簡単に教材や情報が手に入ることもあり「子供のやる気」と「親のやる気」さえあれば塾なしでも充分に高いレベルまで狙えると思います。
塾なし中学受験は集団塾と違い、自分に合わせた計画が立てられる、自分に必要な内容だけを好きなタイミングで学習できるなどメリットがたくさんあります。
こもんがは小6の夏休みまで週5回の習い事を続けながらの塾なし中学受験だったのですが、「自分に必要な学習」に充てた時間は、通塾して同じような難易度の学校に合格した子供達とそれほど変わらないように思います。
それから、中学受験が終わってしばらく経ってから感じたことですが、中学受験で身につけた学習スタイルは中学入学以降も影響するようです。
こもんがの場合、勉強は「人に教えてもらう」というよりは「自分でなんとかするもの」という感覚が強いようで主体的に勉強をしてくれるようになりました。
なので、こもんがにとっての塾なし中学受験は、合否だけでなく、その経験自体がプラスになったとも感じています。
いずれにしても中学受験への取り組みは、各家庭や子供に合っていることが一番大切だと思います。
この記事が、塾なし中学受験に興味がある人の役ににたてば嬉しいです。