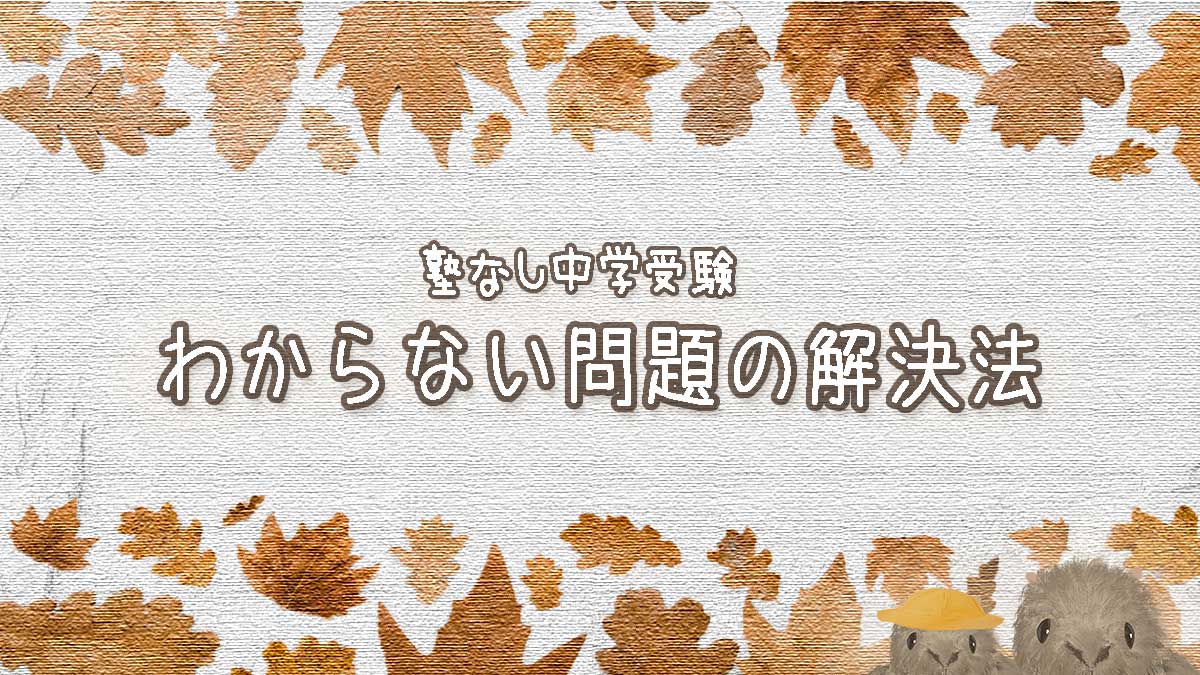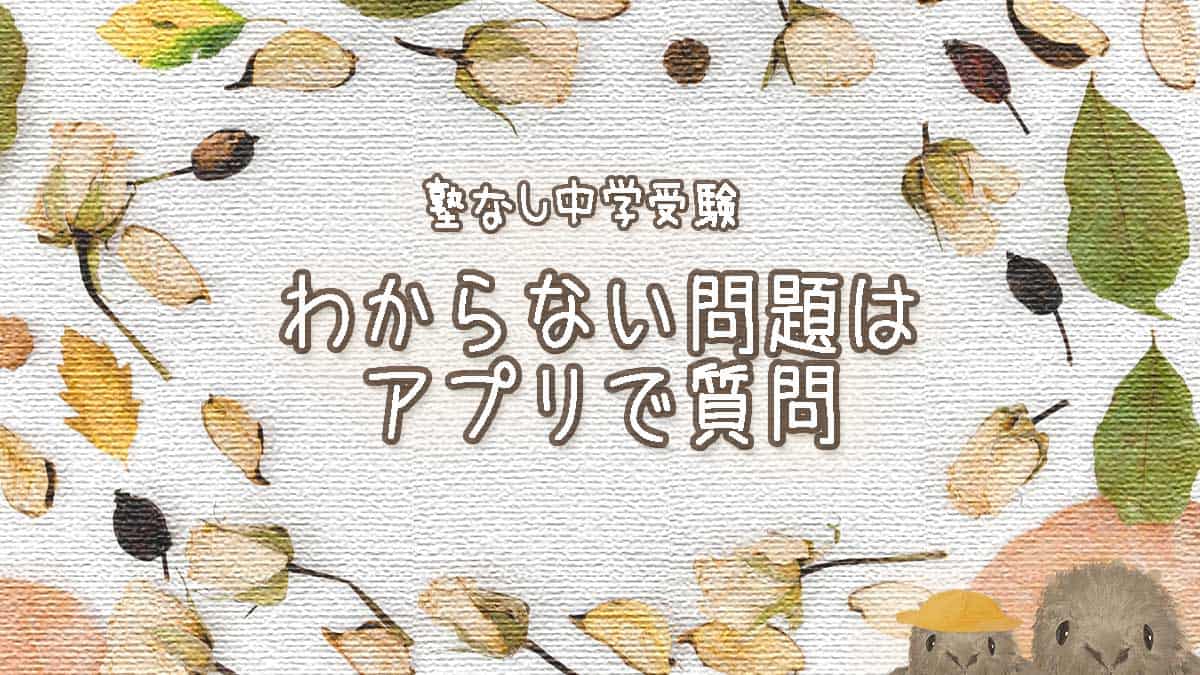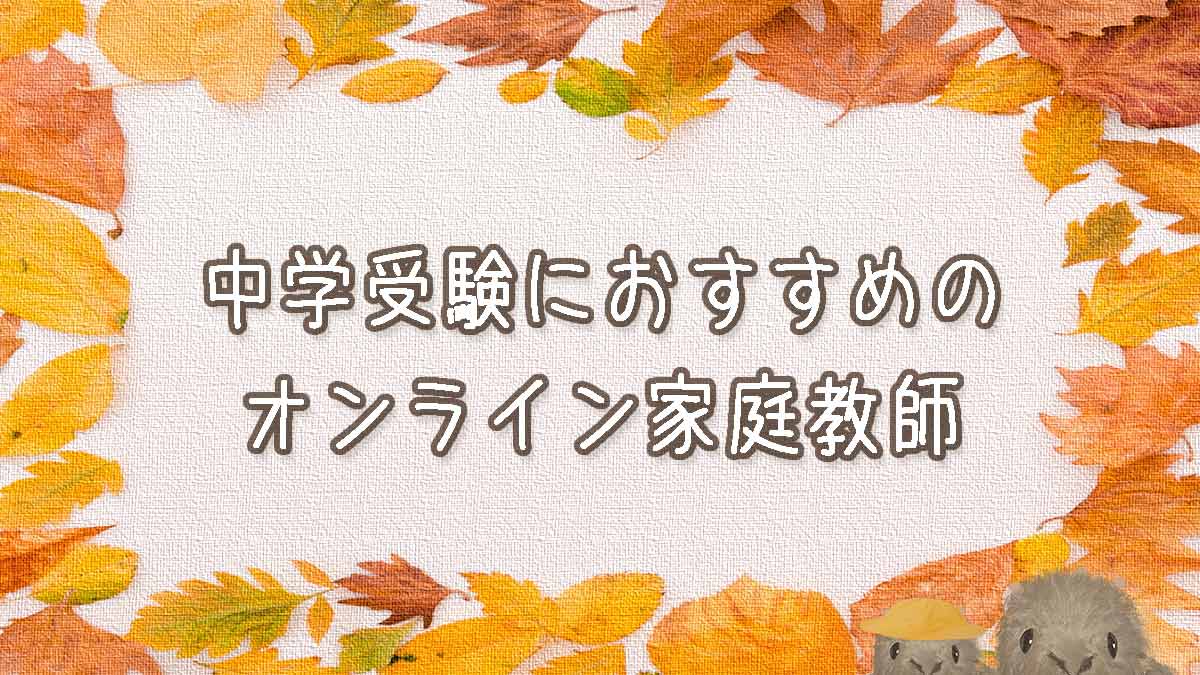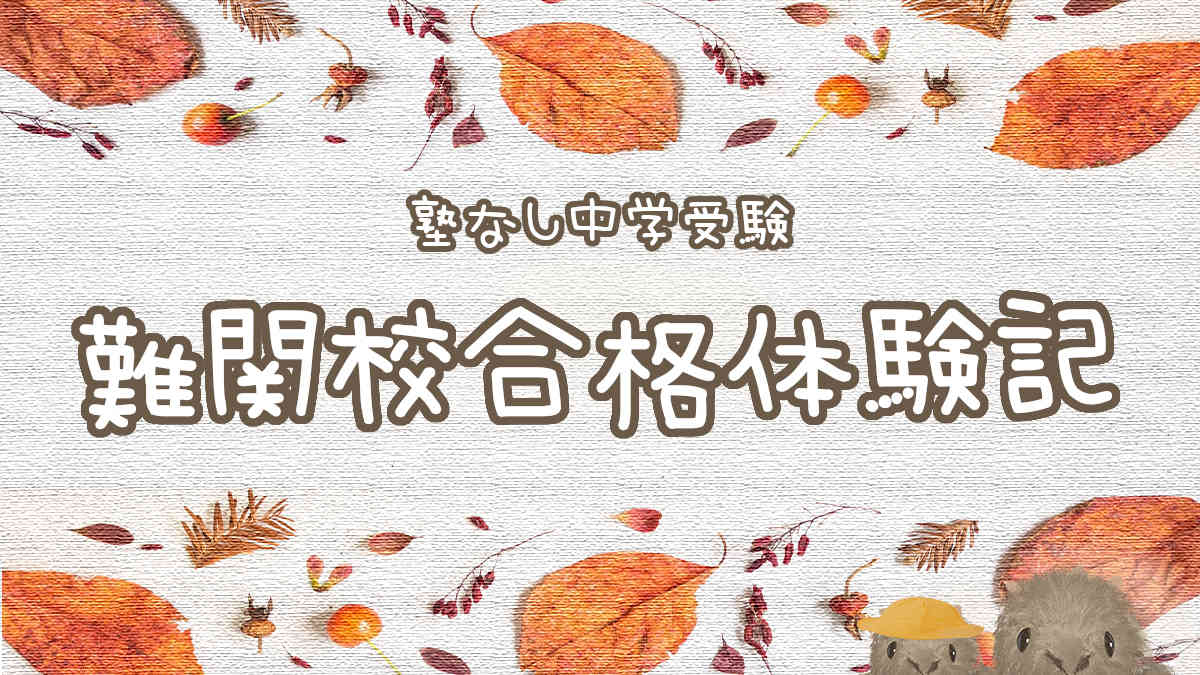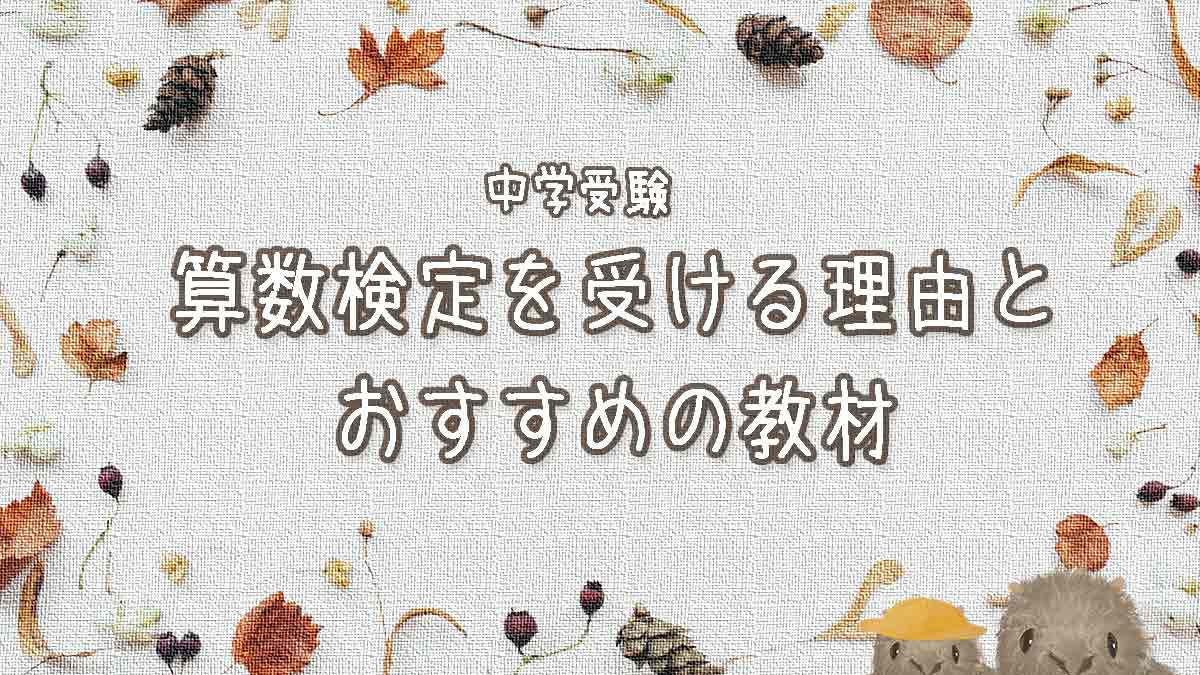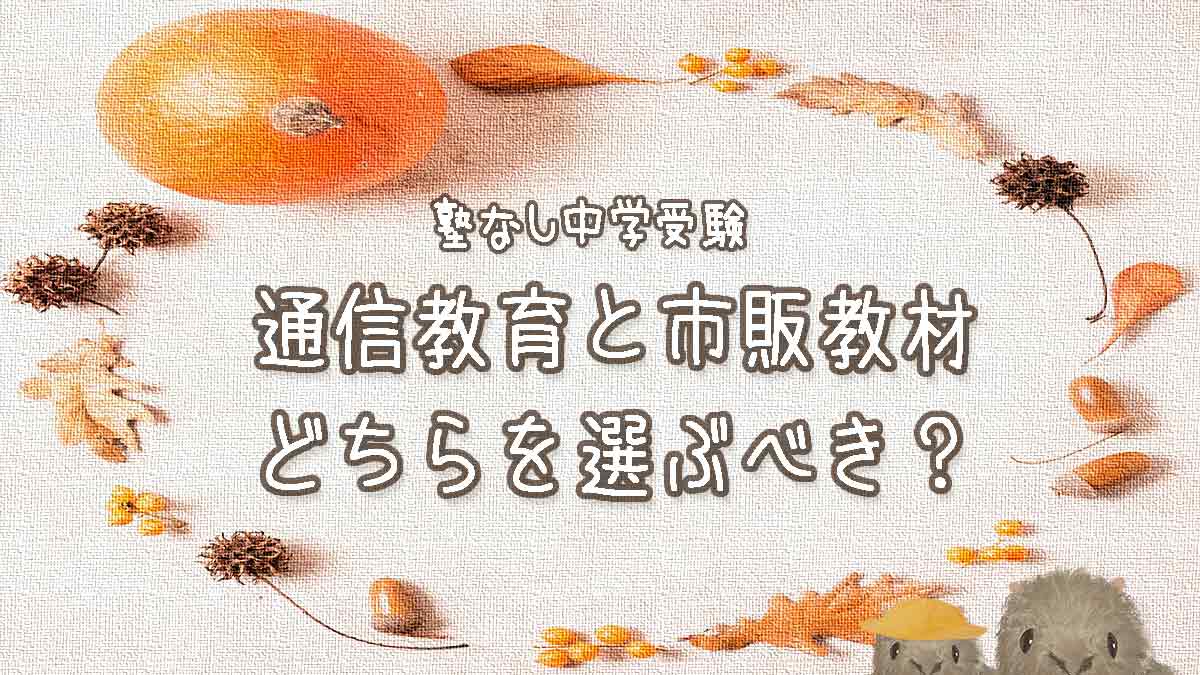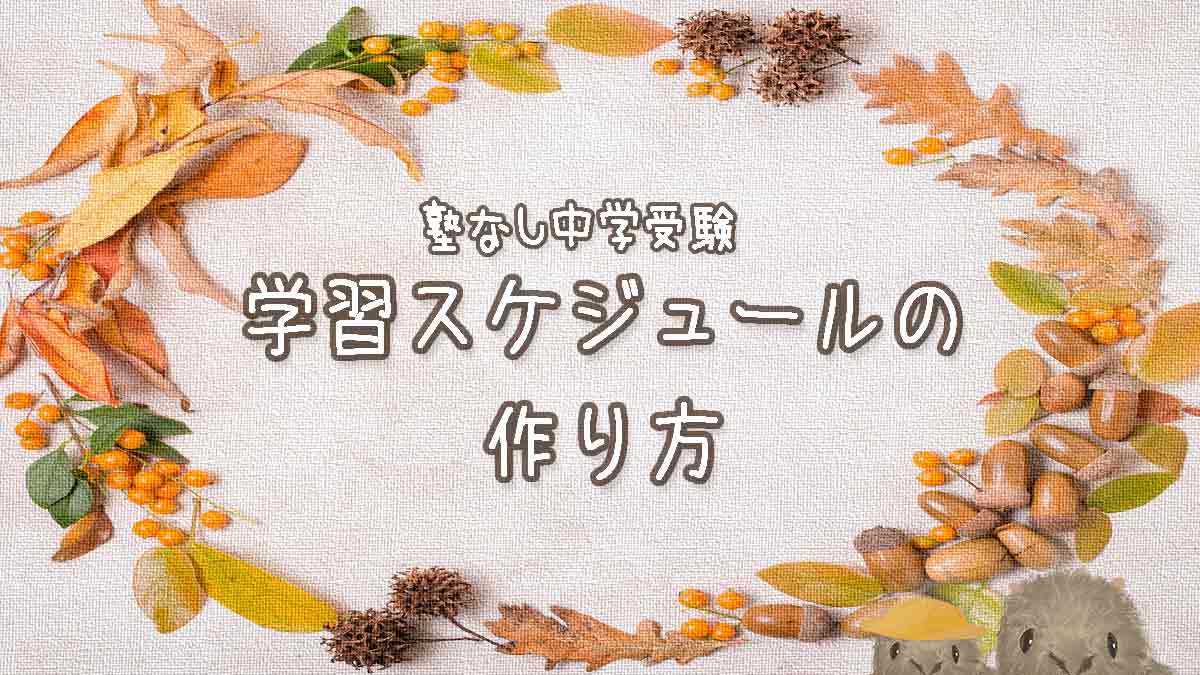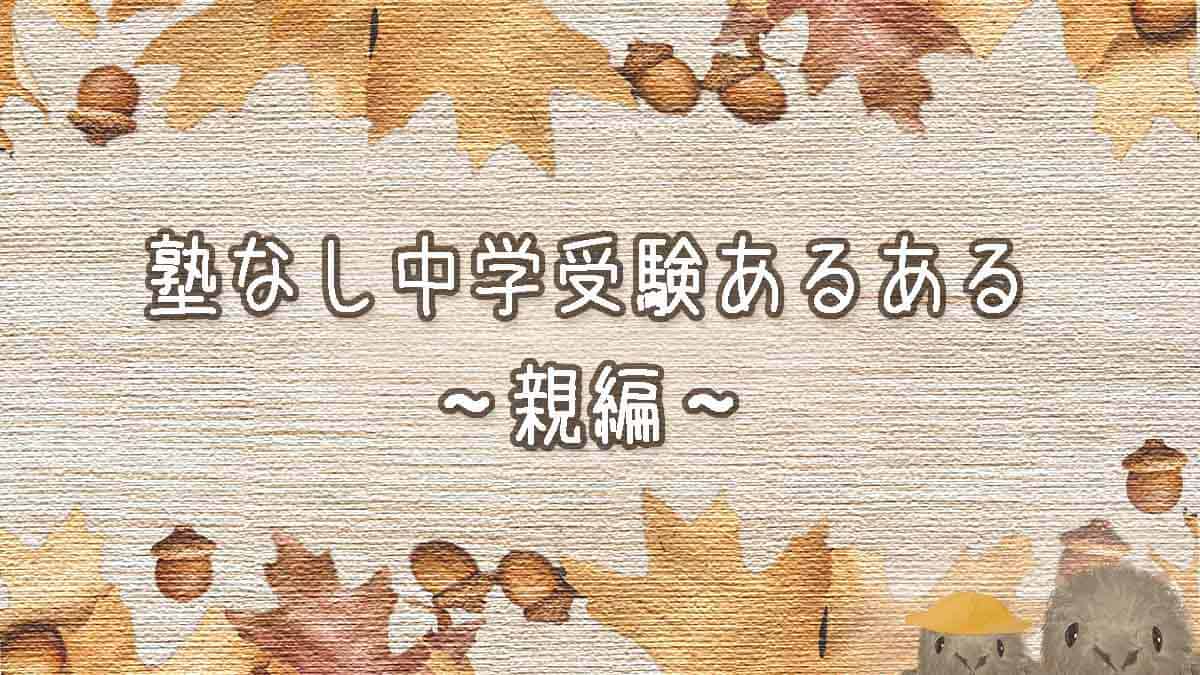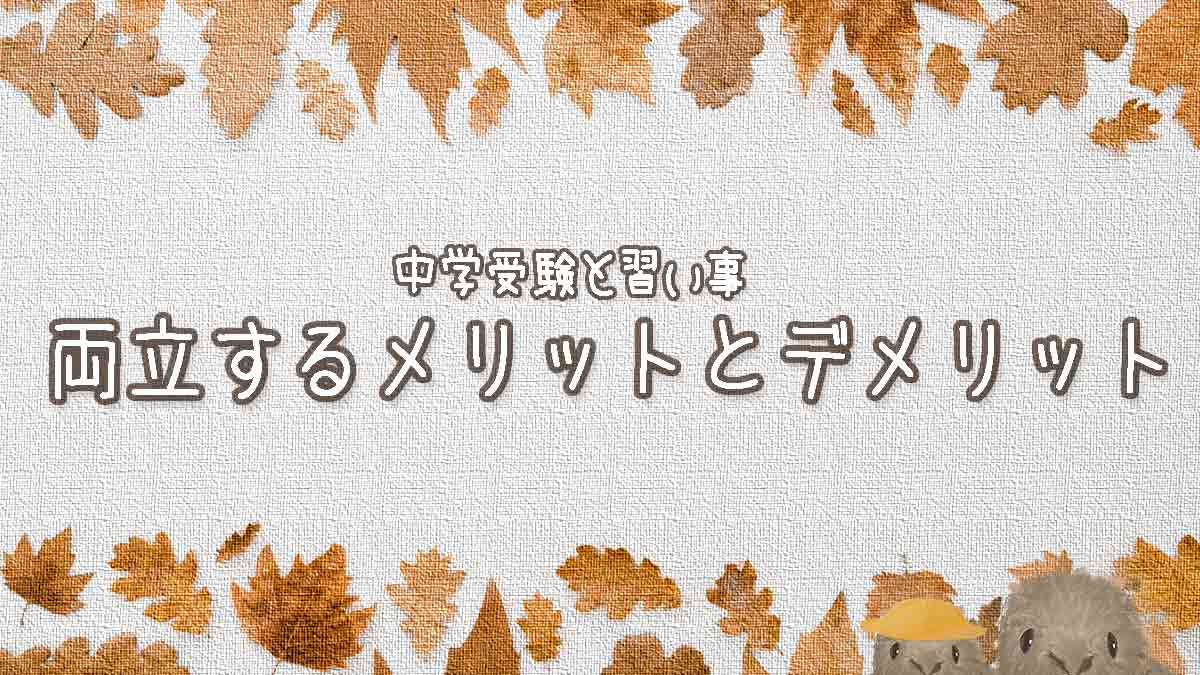「塾なし中学受験をする場合、わからない問題があったらどうすればいいの?」

塾なし中学受験を考えている人にとっては、一番気になるテーマなんじゃないでしょうか?
こもんがは週5回の習い事を小6の夏まで続けながら塾なし中学受験をして、Z会で難関校レベルとされている学校に合格できました。

中学受験向きの教材は良いものがたくさんあるんですけど、共通するのはわからない問題の解決方法に不安が残ることだと思います。
ということで、塾なし中学受験をする場合にわからない問題があった時はどうすれば良いのかを、こもんがが塾なし中学受験をした時の体験談を基に書いていきたいと思います。
問題のレベルを見直す
わからない問題を解決するにはいくつか方法があるのですが、まずは、問題のレベルの見直しです。
塾なしで勉強をする場合、教材や問題集は基本的に自分で選ぶことになります。
でも、問題集や教材ってそれぞれ求められるレベルが違います。
また、同じ教材の中でも基礎を確認するための問題から、基礎が理解できていることを前提とした応用的な問題まで、いろんなレベルの問題が含まれていたりします。
なので、ここを見誤って、基礎を固めなくてはいけない時期に応用問題に取り組んでしまうと、それはできなくて当然です。
そういう時は、自分の実力にあった問題に取り組むようにすると良いです。
スタディサプリをつかって塾なしで中学受験の勉強をしたこもんがも、当初は講義後半の応用的な問題も理解しようとしていたので、時間もかかり、何よりも学習のストレスが大きかったです。
でも、その時の実力に見合った、基礎がために必要な問題に集中してから、ストレスも減り学習がスムーズに進むようになりました。
》スタディサプリを使った中学受験の学習方法と到達レベル〜算数編
とりあえず、飛ばす
あまり良くないことなのかもしれないんですけど、できない問題はとりあえず飛ばして次に行き、テキストを一通り学習したらもう一度挑戦してみるっていうのもありだと思います。
例えば、算数で勉強を始めたばかりの場合だと、計算でまごついたり、問題を図式化する能力や、筋道立てて考える力といったような、問題を解く上で必要になる基本的な作法みたいなものが身についていない場合があります。
なので、とりあえずそのまま努力を続けて、全体的な実力を底上げしてからもう一回挑戦してみよう!っていう感じですね。

こもんがも、最初は話にならなかった問題も勉強に慣れた頃にはできるようになっていたことがよくありました。
繰り返し解いてみる
最初は解けなくても、何度か繰り返していくうちにできるようになっていきます。
繰り返し解きすぎると、問題の解き方を覚えてしまって、あまり理解はできていないんだけど解けてしまう、なんてこともあるんですけど、でも、中学受験はパターン化されている問題が多いので、中堅校くらいまでだったらこれだけでも乗り切れるんじゃないかなっていう印象があります。
こもんがも、最後までちゃんと理解できていなかった時計算は、解法丸暗記で解いていたと思います。
基礎を確認する
一通り基礎を終えて応用問題に取り組むようになってからも、基礎を確認する作業は良いところがたくさんあります。
例えば旅人算や流水算だったら速さ、食塩水だったら割合などなど、もしかしたら一番基礎的な部分の理解に誤りや抜けがあるかもしれません。
しっかりと基礎に戻って確認をしておくと、のちに同じような単元の問題に遭遇した時にも対応できる力がつきます。
この作業は、余計な時間がかかってしまっているように感じることもあるんですけど、単純に抜けている知識を見つけるだけではない利点もあります。
どういうことかというと、どこでつまづいているのかを確認するためには、色々な視点から問題を見る必要が出てきます。
さまざまな角度から問題を考えるというスキルは、複合的な知識を組み合わせる力が必要になる応用問題に取り組むようになった時にとても役立ちます。
思考力を育成することもできるので、人に教えてもらうよりも実力の底上げにはにつながる方法かもしれません。
忍耐力がいる作業なんですけど、時間が許す限り、どこでつまづいているかをしっかりと確認して解消するようにすると、その後の伸びしろにつながります。

子供が幼い場合は、親が隣でサポートしてあげないと厳しいかもですけど、その価値はあります。
捨てる
こもんがの場合、6年生の2学期後半以降は、難易度が高めで理解できていない問題については捨てる選択をしたこともありました。
なぜかというと、時間がもったいないからです。
中学受験は、入試でどれだけ点を取れるかということが明暗につながるので、苦手な問題よりも確実な得点源となる問題に時間を割くようにしていました。
でも、理解できない問題をそのままにしておくっていうのは不安を抱えたまま本番に挑むことになるので、良いところはひとつもないです。
でも、当時はこういった問題を解決する手立てはなく、わからない問題があった時の手段のひとつとして考えるしかない状況でした。
なのですが、時代は変わり、現在はこの問題は解決できるようになりました。
次章から説明していきたいと思います
質問ができるアプリやサービスを利用する
こもんがが進学した学校は、学習の進度も難易度も高く、ほとんどの生徒はなんらかの形で塾に通っています。
でもこもんがは、中学に進学してからも、習い事で多忙だったため塾に通うことはできませんでした。
なので、授業だけで理解できない問題については、空いている時間を使って自分で調べながら勉強をしていました。
でも、この作業って、本当に時間がかかるのです。
それで、わからない問題を質問できる方法ってないのかなと思って探してみたら、あったんです!
いくつかあるので、順番に紹介したいと思います。
ココナラ
ココナラ![]() って聞いたことありますか?
って聞いたことありますか?
個人のスキルを売買するサービスなんですけど、占いから法律相談まで多種多様なスキルが専門家から提供されています。
そして、その中には勉強を教えてくれる塾や家庭教師の講師経験者がいるのです!
従来からある家庭教師的な対応をしてくれる方々もいるんですけど、「わからない問題の質問受け付けます」といった、問題ごとに対応をしてくれる専門家さんたちもいます。
依頼をする前にサービスを受けた人からの講師に対する評価や感想が確認できるだけでなく、案件毎の依頼になるので、合わないと思ったら次回からは頼まないようにすることもできます。
正直なところ、相性が良くない塾の先生や家庭教師に当たってしまい転塾したり、家庭教師の変更に気を揉むといった煩わしさから解放されるのはすごい利点だと思います。
ココナラのサイト、またはアプリで「中学受験」と検索すると中学受験に対応している専門家の一覧が表示されるので、ぜひお試しください。
もし、塾に通っていたとしても、宿題をやっていてわからないところがあったり、違う先生の説明が聞きたい場合なんかにも使えると思います。
ちなみに、登録時の費用や維持費がかかったりすることはなく、あくまでもサービスを受けた分だけ料金を支払うシステムになっているので気軽に試してみてください。
ラクモン
ラクモンは、ココナラのようなスキルマーケット的な作りではなく、わからない問題を質問して解決することに特化したアプリです。
わからない問題を教えてもらうことに特化したサービスなので、質問したい問題の受け渡しや、リアルタイムでオンラインになっている講師に質問ができる点など、ココナラとは比較ににならない使い勝手の良さがあります。
また、iPhoneやiPadなどのIOSユーザーであればリアルタイムでのスポット的な利用だけでなく、気に入った講師を予約してカメラを通して50分間のオンライン家庭教師的な指導を受けることも可能です。
講師陣はいわゆる難関と言われる大学の大学生が多く、おそらく中学受験の経験がある講師が多いのではないかなと思います。
東大や京大、早稲田、慶應などなど、いわゆる難関と言われる大学の講師と直接関わることは、塾なし中学受験を目指している子供たちにとってはモチベーションのアップにもつながると思います。
なお、塾なし中学受験でラクモンを利用する場合は、まずは無料チケットで試してみて、良さそうだったら質問し放題のコースに登録して、中学受験に対応してくれる講師を何人かキープした後に、チケット制にするかそのまま定額制でいくか考えるっていうのがベストな使い方だと思います。
前述したココナラもおすすめなのですが、塾なし中学受験では頼れる手段はできるだけ多く確保しておいた方が良いです。
とりあえずアプリをインストールだけでもしておき、いつでも使える状態にしておくと役に立つ日が来ると思います。
ちなみに、今なら無料で3回までお試し質問ができるほか、カメラを通した授業形式の指導も無料でお試し授業を受けることができるのでぜひ利用してみてください。
オンライン家庭教師を利用する
スポット的な質問だけでなく、もう少し踏み込んだ指導を受けたい、または週1程度でわからないところをまとめて教えてもらいたいといった場合は、自宅にいながら難関大生やプロ家庭教師からの指導が受けられるオンライン家庭教師もおすすめです。
訪問型の家庭教師と違い、家族の負担が少ないだけでなく費用面でも利用しやすい価格設定になっているので、興味がある方は以下の記事を参考にしてみてください。
》中学受験に使えるおすすめのオンライン家庭教師一覧と失敗しない選び方【厳選版】
質問ができるアプリやサービスは心強い味方
塾なし中学受験をするにあたって、教材は動画教材などを利用したICT、紙媒体問わず良いものはたくさんあるんですけど、「質問ができない」っていうのはどちらにも共通する欠点だと思います。
わからない問題にくり返し取り組んだり、基礎を確認して自分で解決していくっていうプロセスはとても有益で、得るものも多いです。
でも、どれだけやってみても、理解できなかったり、丁寧に問題に取り組む時間がない!といった場合は、ココナラのようなスキルマーケットやラクモンのような質問アプリ、オンライン家庭教師はとても役立ちます。
ココナラやラクモンの場合
出品者ごとの評価があり、良さそうな講師を自分で選べる。
相性が悪かった場合は、他の講師に変更することが簡単。
入塾金や指定教材の購入などをする必要がない。
といった共通の利点もあるので、塾との併用を考えた場合でも利用しやすいと思います。
ままんがは、質問系のアプリについてはこの記事で紹介した以外にも色々試したことがあるんですけど、レスポンスが遅かったり、なかったり、メールでやり取りする必要があったり、突然法人対応のみになったり、、、みたいな感じで、それはそれは紆余曲折がありました。
この記事で紹介しているのは、「使える!」と感じたものばかりなので、塾なし中学受験を頑張っている人にも役だててもらえると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

中学受験を考えている人は以下の記事もおすすめです!